あなたも今、こんなことを感じていませんか?
- 「この働き方を、このまま続けていいのだろうか…」
- 「現場は限界なのに、上は何も分かっていない」
- 「やりがいはある。でも心と身体がついていかない」
そんな違和感を抱きながらも、日々の忙しさに流されて、自分の気持ちを後回しにしてしまう――。
私も、ずっとそうでした。
「公務員なんて、辞めるなんてもったいない」「安定してるのに、なんで?」
転職を決断した当時、私の耳にはそんな言葉がよく届きました。
たしかに、公務員という仕事は世間的には“安定”“安心”といったイメージが強いかもしれません。
けれど実際には、現場で働く私たちにしかわからない“限界”があります。
私は元・救急隊員でした。
この仕事に誇りを持っていたし、仲間と命を守る現場で働けることにやりがいも感じていました。
それでも、心も身体も壊れそうになったことが何度もあります。
今回は、私が公務員を辞めた“本音”をありのままに綴ります。
感情的な表現もあるかもしれませんが、それが私のリアルな体験です。
① 組織では「駒」でしかなくなる
ある程度の階級に達しなければ、組織内で意見が通ることはほとんどなく、現場では上からの指示にただ従うだけの日々でした。
特に理不尽だと感じたのは、非番日だったにもかかわらず勤務を続けさせられた出来事です。
その日は夜から雪が降り、出場が相次ぎ、まともに寝る時間も取れないまま朝8時に引き揚げ。
「ようやく交替できる」と思った矢先に次の出場がかかり、渋滞と遠距離搬送でどんどん時間が押し、13時には再び指令が。
限界を迎え、「もう無理です」と訴えても指令は止まりませんでした。
結果的に署に戻れたのは17時過ぎ。不眠不休で1当番以上働かされたあの日は、今でも忘れられません。
② 組織が大きくなるほど「守られる」より「切り捨てられる」
組織にいると、「いざという時は守ってくれる」と思いたくなります。
確かに、公務員という立場には制度上の守られ方や、組織としてのサポート体制もあります。
ただし、それはあくまで“表面上の話”であって、いざ問題が起きれば、結局は個人の責任として処理されることも少なくありません。
現場で起きるミスやトラブルも、その多くは“現場の責任”という形で片付けられ、個人がどれだけ誠実に取り組んでいても、評価よりもリスクや責任追及の空気感ばかりが強く印象に残りました。
「守る」と言いながら、いざという時には距離を置かれる。
その空気感こそが、私にはとても居心地の悪いものでした。
③ 世間体を気にしすぎる文化
公務員という立場は、常に「見られている仕事」です。
そのため、住民からの意見や苦情にはとても敏感で、対応にも細心の注意が払われていました。
もちろん、それ自体は大切なことですし、地域の声を大切にする姿勢は決して間違いではありません。
しかしそれが、「現場の声よりも住民の意見を優先する」という極端な方向に偏ると、実際に動いている職員たちとの間にすれ違いが生まれてしまいます。
私自身、幹部が住民の声ばかりに耳を傾け、現場の課題や疲弊には目を向けてくれなかったと感じたことが何度もありました。
実際の運用に関わるのは現場であり、そこに寄り添わなければ、持続可能な体制にはならないということを強く感じていました。
④ 出る杭は打たれる
少しでも目立つ行動をすると、「余計なことをするな」とたしなめられる。
新しいアイデアを出したり、工夫したりしても、「前例がない」「それは上が決めることだ」と押し返されるばかり。
改善したくても、“空気を読む”ことを求められる――そんな息苦しさがありました。
⑤ 現場の意見が反映されない
現場で感じていた課題や提案が、上層部に届くことはほとんどありませんでした。
たとえ声を上げたとしても、形式や前例を重視する組織の壁に阻まれ、結局は「現状維持」や「上からの指示」が優先される――そんな場面が多々ありました。
また、守るべきことを守るのは組織人として当然だと理解していましたが、
その一方で、「本当に今、それを守ることが必要なのか?」「現場の状況を無視してまで形式を守るべきなのか?」という葛藤を感じることもありました。
現場では柔軟な対応が求められることが多く、実際の状況に即して動こうとしても、ルールや組織の事情によって動きを制限される。
そんな 「現場と組織のすれ違い」が積み重なり、やるせなさや無力感を覚えるようになっていきました。
⑥ 無駄が多すぎる
形だけの書類、誰も見ない資料、見せかけだけの研修――。
やる意味が見出せない“作業”に多くの時間を取られ、本当に必要な業務に集中できないことが多々ありました。
現場では1秒を争う判断を求められる仕事なのに、その裏では何時間も意味のない会議や報告書作成に追われる――。
このギャップには強い違和感を覚えていました。
また、ペーパーレスを推進しているはずなのに、結局は書類を印刷して提出するという場面も少なくなく、「何のためのペーパーレスなのか?」と疑問に感じることもしばしば。
どこの職場にも多少の無駄はあるのかもしれませんが、無駄が無駄を生むような環境が当たり前になっていたことが、
私にはとても効率的とは思えませんでした。
⑦ ストレスが溜まり続ける
休む間もなく出場が続き、心の整理をする時間もないまま、次から次へと命と向き合う現場に向かう毎日。
誰にも弱音を吐けず、感情を押し殺して働き続けるうちに、自分でもストレスの発散方法がわからなくなっていきました。
年々増加する救急要請。
中には「本当に今呼ぶべき内容なのか?」と疑問を抱かざるを得ないケースもあり、現場の疲労感は日を追うごとに強くなっていきました。
ようやく署に戻っても、今度は報告書の作成や事務作業に追われる日々。
肉体的にも精神的にも、どこにも“休まる場所”がないというのが、正直な感覚でした。
⑧ 「いつまでこの状況を続ければ…」という疑問
年々、身体の疲労や精神的なストレスが蓄積していく中で、ふとした瞬間に湧き上がるのが、「この働き方をいつまで続けるのか?」という疑問でした。
このまま定年まで救急隊としてやっていけるのか――。
もし救急隊を外れたら、消防の中で本当に自分がやりたいと思える職種はあるのか――。
そんなことを何度も考えるようになり、自問自答を繰り返す日々が続きました。
「身体は本当に持つのか?」「家族との時間は?」「自分の人生ってなんだ?」いろんな疑問が、少しずつ大きく、そして重くのしかかってくるようになったのです。
そしてある時、ふと立ち止まりました。
「このままじゃダメだ」――
その思いが、退職を意識するきっかけになったのは間違いありません。
⑨ 救急隊のリスクが高すぎる
私たちは、どんな通報があっても、どんな状況であっても「必ず現場に向かう」ことが求められます。
でも、どんな病気かもわからない相手に、真っ先に接触するということは、想像以上に大きなリスクを伴う仕事です。
その恐怖が、はっきりと自分の中に現れたのがコロナ禍でした。
当初は情報も乏しく、感染経路も分からない中で、常に自分が感染するリスクと隣り合わせ。
しかも、万一のことがあったとしても、十分な保障があるわけではありません。
「自分だけならまだしも、もし家族にうつしたら――」そう考えたとき、自分の中で大きな葛藤が生まれました。
信念だけでは守れないものがある。
どれだけ使命感を持っていても、家族を守りたいという思いには勝てなかった。
それが、退職を決断する大きな理由の一つになったのは間違いありません。
■ それでも、この経験があったからこそ
ここまで読んでいただいた方は、「公務員時代に相当な不満を抱えていたんだな」と思われたかもしれません。
実際、そうだった部分もあります。
でも、誤解しないでいただきたいのは――
私にとってあの経験は、今の人生を選ぶために必要な時間だったということです。
厳しい現場に身を置いたからこそ、自分の限界や本音に気づけました。
仲間と支え合った時間があったからこそ、命の重みや人とのつながりの大切さを深く学ぶことができました。
辞めた今だからこそ、公務員としての日々にも『感謝』しています。
あの仕事があったから、今の自分がいる――そう言える自分でありたいと思っています。
■ 最後に
公務員を辞めるという決断は、簡単ではありませんでした。
周囲からの反対もありましたし、不安も当然ありました。
でも、今振り返ると、あの時辞めて本当によかったと思えます。
なぜなら、あのまま組織に留まっていたら、自分が壊れていたかもしれないからです。
今は、自分の人生を自分で選び、自分のペースで歩ける毎日があります。
これは、過去の自分が勇気を出して決断したからこそ、手に入れられたものです。
▼ あなたへ
もし今、同じように悩んでいる方がいれば、声を大にして言いたい。
「あなたの人生は、あなたのものです」
無理に決断する必要はありません。
でも、感じている違和感を、見て見ぬふりはしないでください。
あなた自身の気持ちを、一番に大切にしてほしいと心から思います。
↓↓関連記事はこちら↓↓






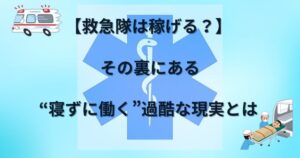
コメント