病院や薬局で払うお金(自己負担)がその月に高すぎたら、決まった上限をこえた分が戻ってくるしくみが『高額療養費』です。
上限は年齢と家計の目安(所得)で変わります。

PR 広告・プロモーションを含みます
高額療養費だけでは“カバーできない出費”があります
差額ベッド代・食事代・交通費…制度で戻らない部分も多いのが現実。
無料の保険見直しで、家族に合う保障を短時間でチェックしておきませんか?
※リンクはアフィリエイト広告を含みます。最新の制度は必ず保険証記載の窓口でご確認ください。
1. どういうしくみ?
- 1か月(1日~末日)ごとに上限額が決まっている。
- その月に払った合計が上限をこえた分は後で払い戻し。
- 70歳以上は外来だけの上限もあって、通院のとき安心。
2. 年齢で分ける → 早見表
A. 70歳未満(5区分・式で出すタイプ)
※下の「医療費」は保険がきく分の10割の金額(窓口の3割負担ではありません)。
※同じような高い月が続くと、4回目から上限が下がる「多数回該当」があります。
| 年収の目安 | その月の上限(自己負担の目安) | 多数回該当(直近12か月で3回超えたら4回目~) |
|---|---|---|
| 約1,160万円~ | 252,600円+(医療費 − 842,000円)×1% | 140,100円 |
| 約770万~1,160万円 | 167,400円+(医療費 − 558,000円)×1% | 93,000円 |
| 約370万~770万円 | 80,100円+(医療費 − 267,000円)×1% | 44,400円 |
| ~約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
家族で合算できる?
同じ保険(例:会社の健保の本人と扶養)なら世帯で合算OK。
ただし、70歳未満は各人の自己負担が2万1千円以上などの条件があります。
B. 70歳以上(外来だけの上限がある)
70歳以上は
- 外来(個人)の上限 … 代表例:「一般」18,000円(非課税の人はさらに低く設定)
- 外来+入院(世帯)の上限 … 代表例:「一般」57,600円(多数回:44,400円)、「非課税」24,600円など
という2本立てです。くわしい区分は保険証の窓口で確認しましょう。
3. かんたん事例
- 40代・年収600万円・その月の医療費(10割)が100万円
→ 上限は 80,100円+(1,000,000−267,000)×1%=87,430円
→ 自己負担は約8.7万円まで。それ以上は後で戻る。 - 75歳・「一般」・通院だけで月2万円
→ 外来(個人)の上限 18,000円。2,000円分は後で戻る。
4. 申請はむずかしい?
- 保険証の窓口(保険者)に電話
「高額療養費の手続きがしたい」と伝える。 - 入院前なら限度額適用認定証をもらう(窓口支払いが上限まででOK)。
- 退院・通院後は申請書+領収書を提出(郵送OKのことが多い)。
ポイント
- お薬代(保険適用分)も合算されます。レシートはまとめて保管。
- 世帯合算・多数回該当など、少し複雑な条件は窓口で教えてもらえます。

5. よくある「つまずき」を先回り
- “10割”と“3割”がごちゃまぜ…
→ 表の式に出てくる「医療費」は10割(保険がきく全部の金額)。窓口で払うのはその1~3割。 - 家族の分は合算できる?
→ 同じ保険なら世帯で合算。70歳未満は2.1万円以上の分が合算対象。 - 毎月高い医療費が続く…
→ 12か月で3回上限に達していれば、4回目から上限ダウン(多数回該当)。
6. 元救急隊としてのひとこと
救急の現場にいた立場から伝えたいのは、「お金の心配が受診のブレーキにならないように」ということ。
高額療養費は、“限度”をあらかじめ決めて家計を守る安全装置です。
入院が決まったら早めに保険者へ連絡して、限度額適用認定証を用意しましょう。
そして、迷ったら受診、緊急時はためらわず119。
家族の不安は、しくみを知ることと手続きを前倒しすることで小さくできます。


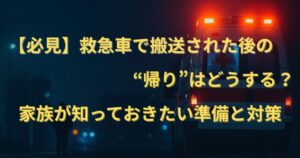
7. この記事の使い方
- 年齢でA/Bを選ぶ
- 年収の目安に近い段をさがす
- その月の支払いが上限をこえたら申請(入院は先に認定証)
注意書き
ここに書いた数字や条件は代表的な目安です。
実際の上限や手続きは、加入している保険(保険者)や世帯の状況で変わることがあります。
最新の内容は保険証に書かれた窓口で必ず確認してください。







コメント