※当サイトのリンクにはアフィリエイト広告が含まれる場合があります。商品・サービスの選定は筆者の経験と独自基準に基づいています。
災害や突然の体調不良は、いつどこで起きるかわかりません。
『救急ポーチ』を準備している家庭は増えていますが、中身が中途半端だったり、家族構成に合っていなかったりするケースが多いのも事実です。
私は元救急隊員として数多くの現場に立ち会ってきました。
その経験から言えるのは、救急ポーチは“なんとなく”揃えるのではなく、家族の年齢や生活環境に合わせてカスタマイズすることが大切だということ。
この記事では、
- 家庭・通勤用
- 子ども向け
- 高齢者向け
の3パターンに分けて、最低限これだけあれば安心という内容をまとめました。
今日から準備できる具体的なリストも紹介します。

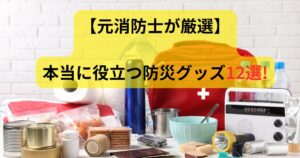
まず揃えるべき『基本セット』
救急ポーチの基盤になるのが『家庭・通勤用セット』です。
自宅や職場、日常の外出で突然の体調不良やケガに対応できる内容を揃えます。
家庭・通勤用に必要な中身
- 絆創膏(S/M/L)・保護パッド
- 滅菌ガーゼ・テープ(紙/布)
- 三角巾または弾性包帯
- 使い捨て手袋(M/L)
- 常備薬(鎮痛薬・整腸薬・抗ヒスタミン薬など)+お薬手帳
- 非接触体温計(夜間でもすぐ測れるタイプ)
- 携帯トイレ(渋滞・災害時に便利)
- ホイッスル(声が届かない環境で役立つ)
👉 最低限この8点を入れておけば、出先でも家庭でも安心です。
選び方のポイント
- 軽さ重視:500g以内に収めると持ち運びが苦にならない
- 仕分け:使用頻度の高い絆創膏や手袋は手前に配置
- 期限管理:半年に一度見直して、薬や体温計の電池を確認
子ども向け救急ポーチ
子どもは大人に比べて『小さなケガ・体調変化』が多く、持ち歩きやすさが特に重要です。
子ども特有のリスクに対応するアイテム
- キャラクター付き絆創膏(気持ちを落ち着けやすい)
- 滅菌ガーゼと低刺激テープ
- ウエットシートやポケットティッシュ
- ラウンド刃のミニはさみ
- 小児対応の携帯トイレ
- 経口補水パウダー・タブレット
- 連絡カード(保護者連絡先・アレルギー情報)
- 防水スマホケース(海・プール・雨対策)
親が持っておくと安心な工夫
- 保護者連絡カードをポーチ内とランドセル両方に
- 小児でも使える携帯トイレは必須。長距離移動や避難所で役立ちます
子ども連れ外出の必携2点
高齢者向け救急ポーチ
高齢者は基礎疾患や服薬があるケースが多く、『薬』『情報』『体調変化の早期発見』が鍵です。
服薬・転倒・体調変化に備えるアイテム
- 常用薬のピルケース(曜日・時間ごとに管理)
- お薬手帳+保険証コピー
- 非接触体温計と体温記録メモ
- 携帯トイレ(トイレ移動が難しいとき)
- 口腔ケア用品(誤嚥予防)
- ホイッスル(声を出しにくい場面で)
- 緊急連絡カード(かかりつけ医・家族連絡先)
受診時に役立つ“情報カード”
『持病・服薬内容・かかりつけ医』をまとめたカードを一枚入れておくだけで、救急隊や病院での対応が格段にスムーズになります。
“声が届きにくい”に備える
あるとさらに安心な+αグッズ
停電や長時間の避難生活では、次のアイテムが力を発揮します。
- モバイルバッテリー(スマホ充電・ライト兼用)
- LEDライト(停電時や夜間移動に)
- アルミブランケット(体温保持)
- マスク・アルコール綿
- 季節用品(カイロ・冷却パック)
停電・長時間移動の実用3点
失敗しない選び方の基準(現場目線)
- 重くしすぎない → 持ち歩かなくなる=無意味
- 触って分かる配置 → 暗所や焦りの中でもすぐ取り出せる
- 測定はスピード命 → 体温計は“押して1秒”が鉄則
- 薬とお薬手帳は同じ袋に → 医師や救急隊に情報を伝えやすい
- スマホ+防水ケース+バッテリーはセット → 連絡・照明・情報収集の生命線
今日そろえる最短ルート

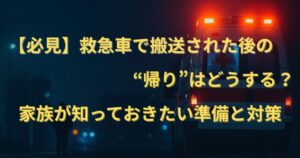
まとめ|3セットを基準に自分仕様へ
- 家庭・通勤、子ども、高齢者、それぞれに応じた3パターンをベースにカスタマイズしましょう
- 救急ポーチは「使うかも」ではなく「必ず役立つ」備えです
- 半年に一度の点検を習慣化すれば、常に“使える状態”を保てます
👉 今日から準備を始めて、いざという時に家族を守れるようにしましょう。
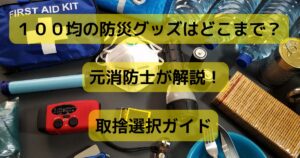


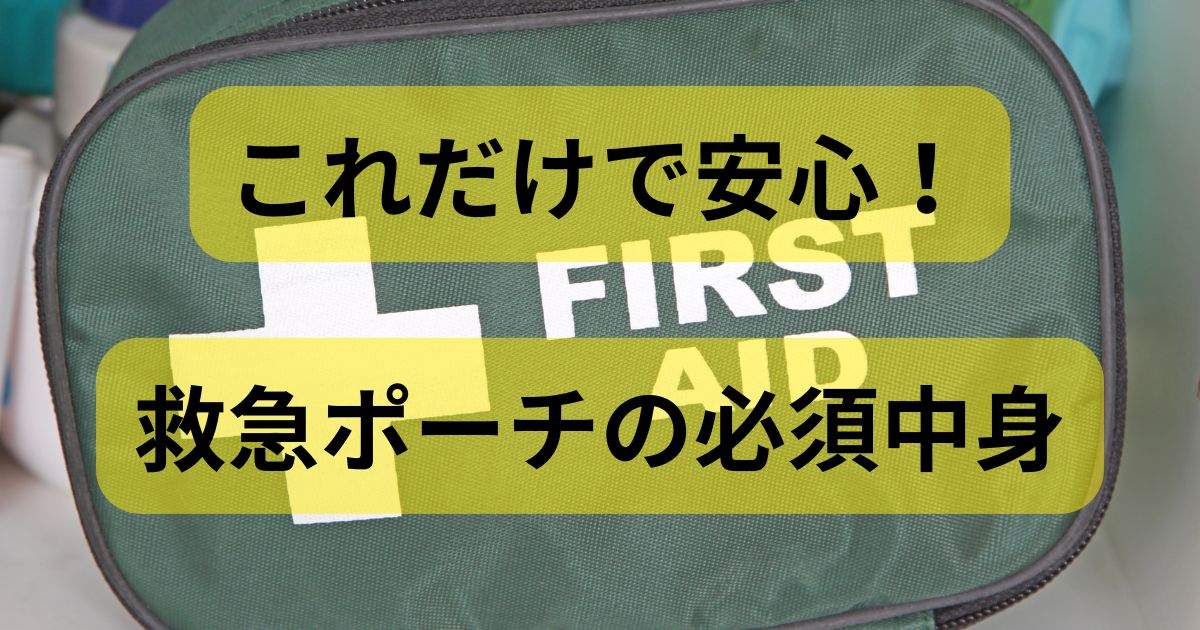
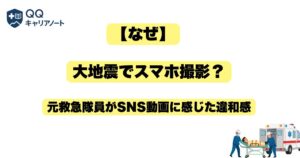
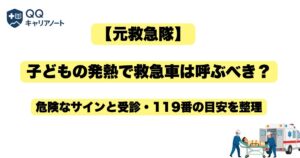
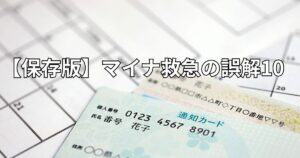
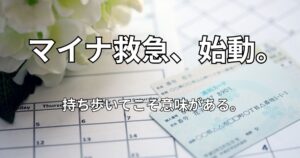
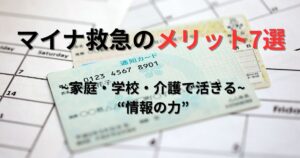
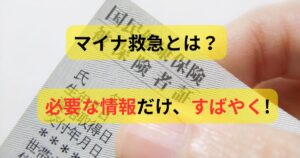
コメント