本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。リンク経由で当サイトが収益を得る場合がありますが、記事内容の独立性は担保しています。
2025年10月1日、「マイナ救急」が全国で正式に開始されました。
マイナ保険証を活用し、救急の現場で必要最小限の医療情報を確認できる仕組みです。
元救急隊員としては、この制度の実現を歓迎します。
しかし同時に「もっと早く導入されていれば…」という悔しさと、登録率の高さだけでは制度は十分に機能しないという課題を強く感じています。
「もっと早く始まってほしかった」現場の声
救急現場では、情報不足が命を左右することがありました。
- 意識を失った高齢者。持病や薬がわからない
- 夜間に独居の方が倒れ、診察券すら確認できない
- 旅行中の外国人が発作を起こしても服薬を伝えられない
こうした場面で「もし情報があれば」と思う瞬間が何度もありました。
マイナ救急が数年前から運用されていれば、助かった命もあったかもしれません。
その悔しさが「もっと早く始まってほしかった」という気持ちに直結しています。
登録率は高いが、持ち歩かれていない可能性
厚労省の公表では、2025年7月末時点で登録者は約8,534万人、登録率は86%超とされています。
数字だけを見れば「すでに多くの国民が登録済み」と言えるでしょう。
しかし、実際の救急現場で本当に役立つかどうかは別問題です。
なぜなら、カードを持ち歩いていなければ救急隊は読み取れないからです。
- 自宅に置いたままの人
- 財布を持たない外出習慣の人
- 災害時に持ち出せなかった人
せっかく登録していても、これでは「実際に使える制度」にはなりません。
自宅では何とかなるが、出先は厳しい
ここで大事なのは、「情報が見つかる環境」の違いです。
🏠 自宅で救急要請する場合
- 診察券・薬袋・お薬手帳がタンスや棚から見つかる
- 家族や同居人が普段の病気や薬を把握している
- 電話の横にかかりつけ病院のメモが貼ってある
→ つまり、自宅なら“手がかり”は何かしら残されていることが多いのです。
🚶 出先で倒れた場合
- 診察券や薬袋は当然手元にない
- 同行者が家族でなければ病歴はわからない
- 旅行者や外国人は、言葉で正確に伝えるのが難しい
→ 出先では情報ゼロになりやすく、救急隊も病院も判断に苦しむケースが増えます。
このギャップを埋めるのが『マイナ救急』の大きな役割です。
だからこそ 「カードを携帯する習慣」 が決定的に重要になります。
【PR】出先で役立つ“携帯”セット
※本パートにはアフィリエイト広告が含まれます。
緊急連絡カード — 連絡先/アレルギー/服薬メモを携帯。
スマホショルダー — 置き忘れ・落下防止。カード・メモも同梱しやすい。
※リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。出先では「情報を持ち歩ける形」にするのがポイントです。
登録率と“使用率”は別物
制度を本当に機能させるには、登録率よりも “使用率” を高めることが重要です。
必要なのは、
- 常に携帯する習慣づけ
- お薬手帳やアレルギーカードといったサブ備えとの併用
- 救急隊・医療機関での端末整備や訓練
登録者数は十分でも、現場で「必要なときに見られるかどうか」は別問題。
このギャップを埋める努力こそが、制度の実効性を決めます。
本当に機能させるために必要なこと
マイナ救急を「救える制度」に育てていくために、私たち一人ひとりができることは次の通りです。
- 家族でマイナ保険証の登録状況と携帯を確認する
- アレルギーカードやお薬手帳をサブ情報として持ち歩く
- 学校や介護施設に最新の健康情報を提出する
- 「カードがなくても救急は来る。でもあるともっと速く正確に」という正しい理解を広める
これらの取り組みが、制度を机上のものではなく「実際に救命に役立つ仕組み」へと変えていきます。
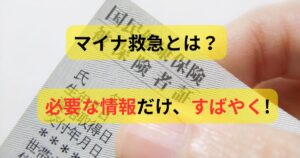
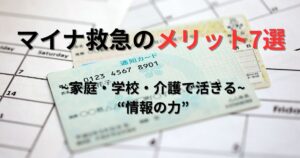
【PR】救急時に“使える”備え
※本パートにはアフィリエイト広告が含まれます。
まとめ
マイナ救急は、長年救急現場に携わってきた私から見ても「待ち望んだ制度」です。
ただし、登録率が高いことだけでは十分ではありません。
- 自宅では診察券や薬袋で何とかなるが、出先では情報ゼロになりやすい
- 携帯してこそ、制度は本当に救命に役立つ
👉 あなたのカードは登録済みですか? そして今、そのカードは手元にありますか?


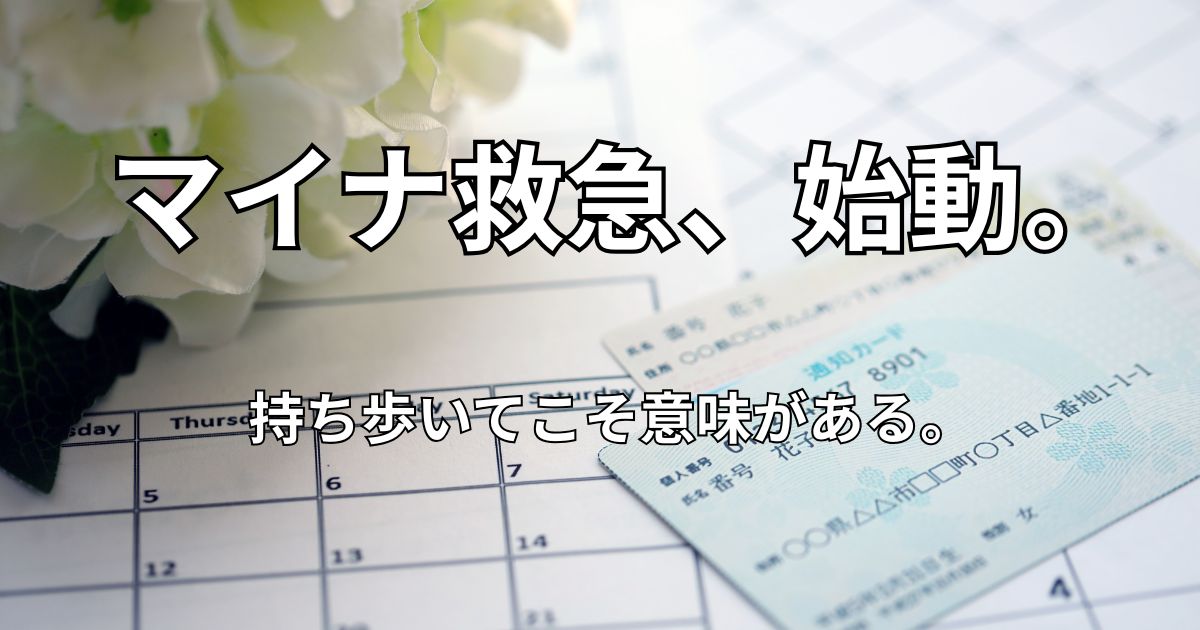
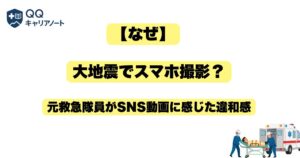
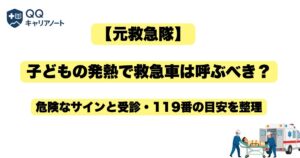
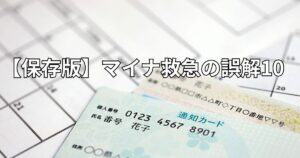
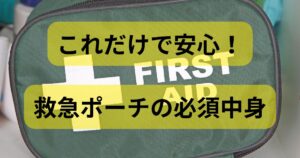
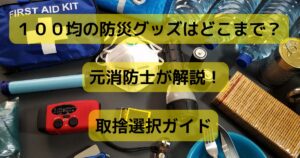
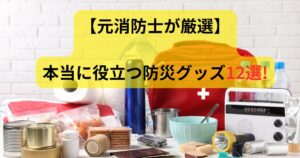
コメント