※本記事にはプロモーション(広告)およびアフィリエイトリンクが含まれます。商品・サービスの詳細は各公式ページをご確認ください。
救急の現場では、わずかな情報の差が命を左右します。
2025年10月から始まった「マイナ救急」は、マイナ保険証を使って救急隊が受診歴や薬の情報を確認できる仕組みです。
正しく理解して活用すれば、処置や搬送がスムーズになり、患者の安全にもつながります。
しかし一方で、「勝手に情報を見られる」「個人情報が病院に流れる」などの誤解や不安も広がっています。
この記事では、救急現場での経験を踏まえつつ、よくある誤解10選と正しい理解をわかりやすく整理しました。
目次
マイナ救急とは?
あわせて読みたい
マイナ救急とは?仕組み・使い方・安心のポイントをわかりやすく解説
救急車で運ばれるとき、病歴や飲んでいる薬がすぐ分かれば、より早く安全に助けられます。 マイナ救急は、マイナンバーカードを保険証として登録している人の必要な医療...
あわせて読みたい
マイナ救急のメリット7選|家庭・学校・介護で活きる“情報の力”
【PR・広告について】 本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。リンクからの購入等により当サイトが収益を得る場合がありますが、記事内容(制度解説・編集方針)に...
まずは概要をシンプルに。
- マイナ保険証を通じて救急隊が 受診歴・処方薬・アレルギー等の医療情報 を確認できる。
- 同意が基本。意識不明など生命に危険がある場合は例外的に参照可能。
- カードがなくても救急活動は通常どおり可能。ただし、あると情報把握がより正確で迅速になる。
- 2025年10月から全国的に実証が進み、段階的に普及が拡大予定。
誤解と正しい理解
誤解1:「同意なしでいつでも勝手に見られる」
→ 正しくは:同意が原則。意識不明などの緊急時に限って例外的に利用されます。
誤解2:「マイナンバー(12桁)で追跡される?」
→ 正しくは:救急隊が現場で利用するのはマイナンバー(12桁)ではありません。
救急隊が読み取るのは マイナ保険証のICチップに保存された情報 であり、そこから医療情報を確認します。
さらに、この利用履歴は マイナポータルで本人が確認可能。
よって、マイナンバーそのものが追跡に使われることはありません。
誤解3:「税金や年金の情報まで丸見え」
→ 正しくは:参照できるのは医療分野の情報のみ。税や年金、収入の情報は表示されません。
誤解4:「過去の病歴がすべて暴かれる」
→ 正しくは:参照できるのは診療・薬剤の要点をまとめた“救急用サマリー”。無制限ではなく必要最小限です。
あわせて読みたい
【2025年最新】救急車有料化はいつから?元救急隊員が解説する実施スケジュールと影響
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます 私はかつて救急隊員として、何千件もの出場に携わってきました。 命の危機に直面する現場もあれば、「ちょっと熱があるから...
あわせて読みたい
【図解】選定療養費とは?かかる/かからないケースをわかりやすく解説
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 「救急車を呼ぶとお金がかかるのでは?」と思う方も多いですが、救急車の利用は無料です。 実際に費用がかかるのは ...
あわせて読みたい
救急車で1万円⁉知らないと損する『選定療養費』の実例と備え方
もし救急車で搬送された後、1万円以上を請求されたら――あなたは驚くでしょうか? 2025年現在、救急車を呼ぶこと自体は全国どこでも無料です。 しかし一部地域では「軽症...
誤解5:「カードがないと搬送できない」
→ 正しくは:カードがなくても救急活動は問題なく行われます。マイナ救急はあくまで“プラスアルファ”です。
誤解6:「救急から病院へ個人情報が勝手に流れる?」
→ 正しくは:必要な情報だけが伝えられる仕組みです。
救急隊は、参照した情報をもとに搬送先を決めたり、処置を行うために必要な内容を口頭で医療機関に伝えます。
また、病院の医師は「救急時医療情報閲覧機能」を使い、意識不明などの緊急時に限って詳細な情報を参照可能。
つまり、「勝手に流れる」のではなく、救命のために必要な範囲でのみ利用される仕組みです。
あわせて読みたい
#7119の正しい使い方|聞かれることリスト&話し方テンプレ(保存版)
#7119は、救急車を呼ぶべきか/今すぐ受診すべきか迷ったときに相談できる電話窓口です。 医師や看護師などの相談員が症状を聞き取り、緊急性の目安や受診先の案内をし...
あわせて読みたい
旅行先などで体調不良になったら|#7119の代替手順と“受診メモ”&最低限の持ち物
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 旅行や出張の最中に具合が悪くなると、土地勘がなく「どこに連絡?どう受診?」でパニックになりがちです。 この記事...
あわせて読みたい
救急車「呼ぶか迷ったら」どうする?つながらない#7119と備える知識
「これって救急車を呼ぶべきなのかな…」 急な体調不良やケガの際、判断に迷った経験はありませんか? そんなとき頼りになるのが「#7119(救急安心センター)」です。 医...
誤解7:「都市部だけ。地方では当分使えない」
→ 正しくは:全国で実証が始まっており、段階的に各地域にも広がっています。
誤解8:「圏外や停電で使えないと危険?」
→ 正しくは:マイナ救急が使えなくても、救急活動は通常どおり行われます。
政府も「マイナ救急は追加の“プラス”」と説明しています。
従来どおり、観察や聞き取り、バイタル測定などで対応できるので「止まったら危険」というのは誤解です。
あわせて読みたい
【元消防士が厳選】本当に役立つ防災グッズ12選!最低限で72時間を生き延びる
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 災害現場では『光・通信・水/トイレ・衛生』の確保が最優先です。 元消防士として数多くの現場に立ち会ってきた経験...
あわせて読みたい
【2025年版】救急ポーチの中身はこれで足りる|子ども・高齢者・通勤用の3セット
※当サイトのリンクにはアフィリエイト広告が含まれる場合があります。商品・サービスの選定は筆者の経験と独自基準に基づいています。 災害や突然の体調不良は、いつど...
誤解9:「同意は必ず書面で必要」
→ 正しくは:現場では口頭同意で十分。迅速さを損なわない仕組みになっています。
誤解10:「カードを落としたら悪用される」
→ 正しくは:ICチップの情報を読み取るには暗証番号等が必要。紛失時は24時間体制で利用停止も可能です。
補足情報:安心して使うために
- 家族で合意しておく
「意識がある時は同意する」「意識がない時は救命目的で利用してよい」など、あらかじめ決めておくと安心です。
- 携行方法を固定する
財布やスマホショルダーなどに常に入れておき、忘れや紛失を防ぐ。
- アナログ補助も準備
緊急連絡カードやお薬手帳を持ち歩けば、停電・圏外の時も役立ちます。
- 地域の運用状況を確認
市区町村や消防の案内をチェックして、自分の地域の導入状況を知っておきましょう。
あわせて読みたい
大雨・洪水のときに命を守る行動|避難のタイミングと絶対してはいけない危険行為
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます 大雨や洪水は「いつもの雨」と思った瞬間に命を奪う脅威へと変わります。 元救急隊員・消防職員として活動してきた中で私は...
あわせて読みたい
水泳教室の監視体制に疑問 〜親として・元救急隊員として考える安全対策〜
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 水の事故は夏だけのものではありません。 学校の授業で使うプール、スイミングスクール、温水プール、さらには家庭用...
【PR】医療費・就業不能に備える保険(広告)




※各リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。詳細は各サービスの重要事項説明・約款をご確認ください。
まとめ:命を守るための数秒を縮める仕組み
マイナ救急は、
- 同意が基本、例外は救命時のみ
- 参照できる情報は医療に必要な範囲に限定
というルールのもとで運用されています。
「勝手に全部見られる」という不安は誤解です。
この仕組みはあくまで “命を守るための数秒を縮める” ためのもの。
日頃からカードを携帯し、家族で「救命時には利用して良い」と合意しておくことが、最も正しい準備といえるでしょう。
あわせて読みたい
マイナ救急とは?仕組み・使い方・安心のポイントをわかりやすく解説
救急車で運ばれるとき、病歴や飲んでいる薬がすぐ分かれば、より早く安全に助けられます。 マイナ救急は、マイナンバーカードを保険証として登録している人の必要な医療...
あわせて読みたい
#7119の正しい使い方|聞かれることリスト&話し方テンプレ(保存版)
#7119は、救急車を呼ぶべきか/今すぐ受診すべきか迷ったときに相談できる電話窓口です。 医師や看護師などの相談員が症状を聞き取り、緊急性の目安や受診先の案内をし...
あわせて読みたい
世界の「救急車は有料?無料?」国別比較と旅行保険の要点【2025年版】
日本では「救急車=無料」が当たり前。 ですが一歩海外に出ると、国や州によって“無料/有料/一部負担”が大きく違うのが現実です。 さらに同じ国の中でも州・準州・県・...
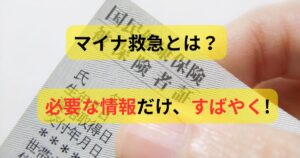
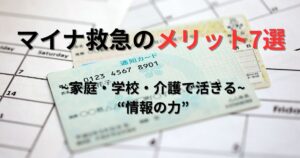






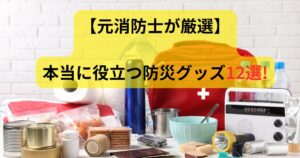
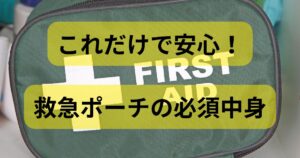


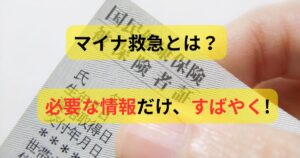
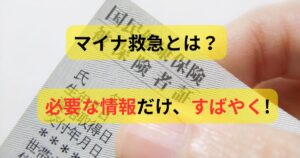




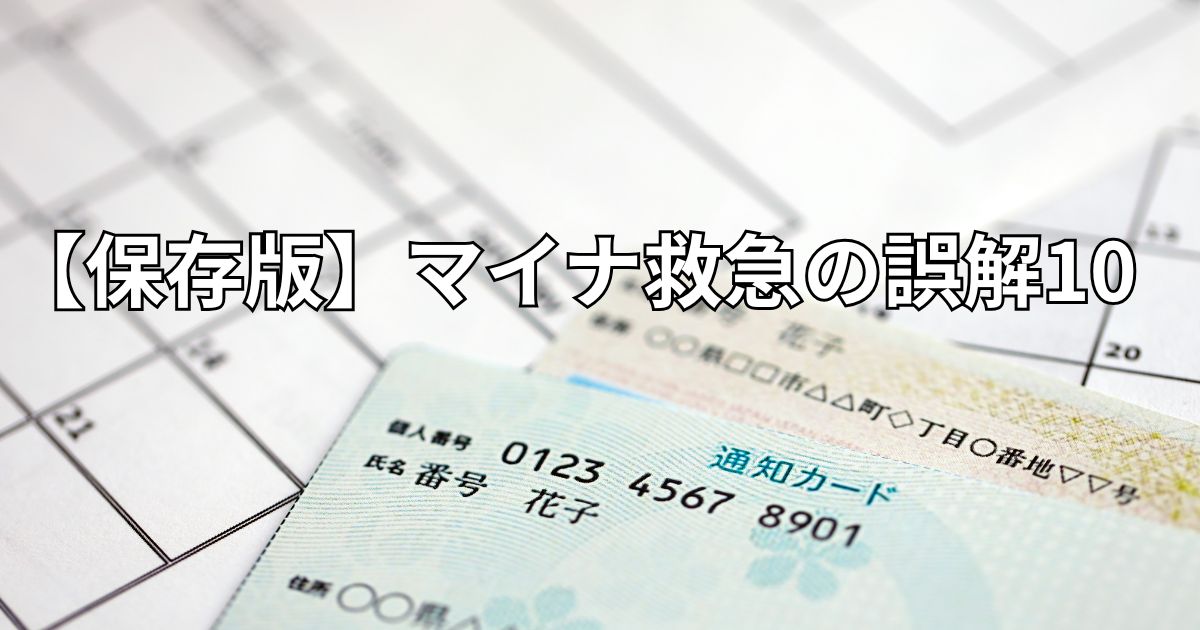
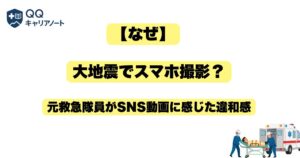
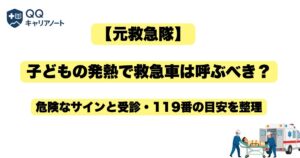
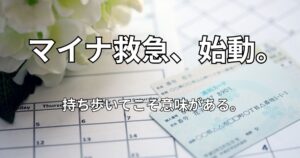
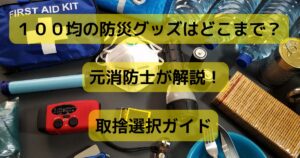
コメント