※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます
私はかつて救急隊員として、何千件もの出場に携わってきました。
命の危機に直面する現場もあれば、「ちょっと熱があるから念のため…」
という軽症の方の搬送も少なくありませんでした。
そのたびに思ったのは、「この出場が、本当に必要だったのか?」という問いです。
2025年現在、全国で救急車の有料化に向けた動きが加速しています。
この記事では、実施スケジュールや各自治体の取り組み、そして現場目線での影響について、わかりやすく解説します。
👉 関連:救急隊の態度が悪い?誤解が生まれる理由と本音

🗓️ 救急車有料化はいつから?実施スケジュールまとめ
全国一律の有料化はまだ決定されていませんが、
一部自治体ではすでに導入が始まっており、2025年も新たな動きが出ています。
実施済み・進行中の自治体
| 地域 | 開始時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 三重県松阪市 | 2024年6月〜 | 入院が不要と判断された場合、患者に7,700円を負担。軽症者向けの搬送費用として病院側が徴収。 |
| 茨城県 | 2024年12月〜 | 緊急性のない軽症者から費用徴収(1,100円〜13,200円)。 |
| 大阪府 | 2019年4月〜 | 入院不要の場合、5,000円を徴収。 |
| 神奈川県 | 2020年4月〜 | 同様に8,000円を徴収。 |
これらは「選定療養費制度」を活用したもので、消防ではなく病院側が費用を徴収しています。
🏙️ これから動き出す自治体の最新情報
2025年現在、以下の自治体が有料化に向けた検討を進めています:
| 自治体 | 現状・検討内容 | 目的・狙い |
|---|
| 東京都練馬区・杉並区 | 救急車の適正利用を啓発中。将来的な有料化を見据えた準備段階。 | 軽症者の利用を減らす 医療資源の無駄を防ぐ |
| 名古屋市 | 民間救急車の活用を進め、公共の救急車との役割分担を検討。 | 公的救急車の負担軽減 効率的な搬送体制の構築 |
| 津市(三重県) | 松阪市の事例を参考に制度設計を検討中。 | 軽症者搬送の費用負担検討 医療資源の最適化 |
| 横浜市 | 専門学会で有料化に関する討論が行われ、賛成多数。 | 軽症者利用の抑制 制度導入の可能性検討 |
これらの自治体では、「軽症者の抑制」や「医療資源の最適化」を目的に、段階的な導入が進む可能性があります。
👉 救急車で1万円⁉ 知らないと損する『選定療養費』の実例と備え方

⚖️ 有料化のメリットと懸念点
🧰 すぐ準備できる“受診時短”アイテム
- お薬手帳ケース:診察券・保険証・医療証をひとまとめ。受付〜トリアージがスムーズ
- 救急ポーチ:絆創膏・ガーゼ・ハサミ等を携行。軽外傷や応急処置に
お薬手帳ケース
救急ポーチ
※上記リンクはアフィリエイト広告を含みます。リンク経由でもご利用者の支払額は変わりません。
メリット(現場から見た実感)
- 本当に必要な人に迅速に対応できる
- 無駄な出動が減り、隊員の負担軽減
- 医療費の抑制にもつながる
懸念点
- 経済的理由で利用をためらう人が出る可能性
- 症状の軽重を自己判断することが難しく、トラブルにつながる場合も
- 「お金を払っているから」とタクシー代わりに使う人が増える懸念
現場では「救急車を呼ぶべきか迷った」という声を何度も聞いてきました。
有料化によって迷いが命に関わる判断ミスにつながらないよう、慎重な制度設計が求められます。
💡 高額療養費の自己負担上限“早見表”

🌍 海外の事例と日本の違い
- アメリカ:救急車利用に数万円以上かかることも。保険未加入者には大きな負担。
- フランス・ドイツ:医療保険で費用がカバーされ、利用者負担は少ない。
- イギリス:基本的に無料だが、対応の遅れが課題。
日本は「誰でも無料で呼べる」という安心感がありますが、制度の限界も見えてきています。
📞 #7119の正しい使い方|聞かれることリスト&話し方テンプレ

PR 広告・アフィリエイトを含みます
“制度のスキマ”は保険で埋める
選定療養費や通院費、収入減リスクまで—家族に合う保障を短時間で比較。
無料の保険見直しで、今の備えで足りるか一度チェックしませんか?
※リンクはアフィリエイト広告を含みます。制度・金額は地域や条件で異なる場合があります。
🧭 最後に:元救急隊員として伝えたいこと
救急車は『命をつなぐ最後の砦』です。
しかし、その砦が軽症者の利用で揺らいでいる現状を、私は現場で何度も目の当たりにしてきました。
有料化は決して『冷たい制度』ではなく、本当に必要な人に救急車が確実に届くための仕組みです。
ただし、制度を導入する際には、丁寧な説明と住民の理解が不可欠です。
これからも、救急車が「命をつなぐ存在」であり続けるために、私たち一人ひとりが『適正利用』を意識することが何より大切です。
↓↓関連記事はこちら↓↓
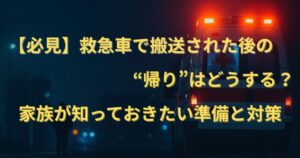








コメント