夜間・休日に子どもが急にぐったり。
そんなとき、“すぐ手に取れる”準備が心の余裕と適切な判断を生みます。
ここでは、元救急の視点で本当に使える常備品を「理由・選び方・使い方のコツ」までまとめました。
迷ったら #7119(小児救急電話相談)、緊急時はためらわず 119 へ。
迷ったときの相談先 👉 #7119の正しい使い方(保存版)

迷ったらここだけ
- 非接触体温計:寝ていても測れる/ワキ計との二刀流で誤差を減らす
- 経口補水液(ORS):脱水予防の基本。年齢に合ったタイプを常備
- 瞬間冷却材:すぐ冷える携帯冷却。直接肌に当てずタオルで包む
注記(#7119は地域差あり):お住まいの地域によって対応時間や接続条件(ダイヤル回線・一部IP電話不 可など)が異なります。
自治体の#7119案内ページを事前に確認し、代替の直通番号があればスマホにメモ/ブクマしておきましょう。
注意:本記事は一般情報です。持病や月齢、薬の飲み合わせによっては使えないものがあります。判断に迷う・ぐったり・水分が取れない・呼吸が苦しい・けいれん・顔色不良などは直ちに119。
1) まずは「計測・記録」から
① 非接触体温計(+接触式のサブ)
- あると助かる理由:小さな子はワキで測るのを嫌がる/夜間の寝込み測定がしやすい。
- 選び方:測定距離・角度の指定が明確/バックライト付き/音が消せると夜間に便利。
- わき/耳式も1本あるとダブルチェックでき安心。
- 使い方のコツ:汗・泣いた直後は誤差が出やすい/複数回測って平均をイメージ。
- 一緒に:アルコール綿・替えカバー・予備電池。
- 現場メモ(救急隊):ワキに体温計を挟もうとすると泣いて拒否する子が非常に多い。
まず非接触で検温→落ち着いたら、わき式で再確認がスムーズ。
乳児はぬいぐるみや人形でご機嫌をとりながら観察すると安全に進めやすい。
親御さんにわき式を挟んでもらうと成功率が上がります。
※本記事内のリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
非接触体温計
② タイマー&メモ(スマホでOK)
- 理由:「いつから・何を・どれだけ」 は医師に伝える超重要情報。
- メモ項目:発症時刻・体温推移・水分量・尿回数・解熱剤の種類と投与時刻。
2) 冷却・体温調整
③ 瞬間冷却材
- 理由:外出先でも“すぐ冷える”。不快感の軽減、搬送時にも。
- コツ:直接肌に当てない(ガーゼや薄手タオルで包む)/長時間の当てっぱなしは避ける。
※本記事内のリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
瞬間冷却材
④ 冷却シート(子ども用)
- 役割:高熱を下げる “薬” ではなくラクにするアイテム。就寝時の不快感軽減に。
⑤ ガーゼ/小さめタオル複数
- 活躍:汗拭き・冷却の当て布・吐物対応に万能。色違いで用途分けすると衛生的。
3) 補水・栄養
⑥ 経口補水液(ORS)
- 理由:脱水予防の第一選択。下痢・嘔吐・発熱時の基本。
- 選び方(重要):必ず月齢・年齢に合った製品を選ぶ。
乳幼児に大人用ORSをそのまま与えるのは避ける(電解質バランスが崩れる恐れ)。
パウダータイプは表示どおりの量で正確に調製し、自作レシピは推奨しない。 - コツ:少量を頻回(スプーン1杯〜)/冷やしすぎない/吐いた直後は10〜20分休んでから再開。
- 期限管理:ラベルに「YY/MM」 を書いて定期入替。
- 親メモ:普通のコップだと飲まないとき、ストローやキャラクターのコップに替えるだけで飲みが進むことがあります(無理強いは×)。
※本記事内のリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
経口補水液
⑦ ゼリー飲料(子ども向け)
- 位置づけ:食欲が落ちた時の “つなぎ”。ORSが優先、ゼリーは補助的に。
⑧ ストローカップ/シリコンストロー/経口シリンジ
- 理由:むせにくい姿勢・角度で少量ずつ飲ませやすい。
- コツ:横抱きで顎を少し上げず、自然な角度で。
4) 衛生・片づけ
⑨ 使い捨て手袋 & マスク(子ども用/大人用)
- 理由:嘔吐・下痢時の二次感染予防。家族内感染の拡大を防ぐ。
⑩ 大判ペットシーツ/古タオル & 防臭ビニール袋
- 使い道:吐物・下痢での床/布団保護 → そのまま包んで処分。
⑪ 除菌シート & 消毒用アルコール
- 用途:手指・ドアノブ・テーブルなどの拭き取り。子どもが触れる場所から優先。
5) 応急・便利グッズ
⑫ 鼻吸い器(乳幼児) & 生理食塩水スプレー
- 理由:鼻閉で眠れない・飲めないのを緩和。QOLが段違い。
- コツ:取説どおりやさしく短時間で/嫌がる時は無理をしない。
⑬ 体温計ケース & 予備電池
- 理由:いざという時の電池切れ防止/持ち出しやすい。
⑭ 小型ライト(ペンライト程度)
- 用途:夜間の状態確認、のどの観察、吐物の確認。
⑮ 小児用解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン)
- 重要:年齢・体重に合う製剤を用法用量厳守。生後3か月未満の発熱や初めての発熱では、自己判断での使用は避け、まず医療機関へ。
- 座薬と内服の関係:同じ体重あたり量なら効果は同等。使いやすい方でOK。
- 間隔:次に使えるまでの時間(通常は6時間以上)を厳守。製品ごとの用法も必ず確認。
- 重複注意:かぜ薬など成分が重なる製品を併用しない。
- 避ける:アスピリン系(ライ症候群リスク)/自己判断の座薬連投。
#7119/受診の目安
- #7119:都道府県の小児救急電話相談。症状の聞き取りから受診の要否、受診先の相談に乗ってくれます。
- 地域差に注意:24時間対応でない地域があります。加えてダイヤル回線や一部のIP電話からは繋がらない場合も。お住まいの自治体ページで事前確認し、代替の直通番号が案内されていれば控えておきましょう。
今すぐ119のサイン:- ぐったりして反応が弱い/意識がはっきりしない
- 何度も吐く・水分が取れない・尿が極端に少ない
- 呼吸が苦しそう・ヒューヒュー音・唇が紫
- けいれん・高熱が続く(特に生後3か月未満の発熱)
- 強い腹痛・首の硬さ・発疹が急に増える
病院へ行くときの持ち出しセット
- 保険証・医療証・母子健康手帳・お薬手帳
- 体温・水分・服薬のメモ(スマホでも可)
- 着替え・おむつ・おしりふき・ビニール袋
- 経口補水液・ゼリー・ストローカップ
- 充電ケーブル/モバイルバッテリー
収納と在庫管理のコツ
- 透明ケース1つにまとめ、フタ裏にチェックリストを貼る
- ORS/ゼリー/冷却シートは期限ラベル(YY/MM)を貼る
- 季節の変わり目に“入れ替え日”を家族カレンダーで共有
- 体温計・ライトは予備電池を同梱
チェックリスト
- 非接触体温計/ワキ・耳式体温計
- 予備電池(体温計・ライト用)
- 経口補水液(年齢に合う製品)
- ストローカップ/シリコンストロー/経口シリンジ
- 瞬間保冷剤+ガーゼ/小タオル(直接当てない)
- 冷却シート(ラクにする目的)
- 使い捨て手袋・マスク
- ペットシーツ/古タオル/防臭袋
- 除菌シート/消毒用アルコール
- 小児用アセトアミノフェン(用法・間隔6時間以上)
※可能ならばチェックリストを印刷して冷蔵庫などに貼るのもおすすめです。
まとめ
- まず3点:非接触体温計/ORS(年齢適合)/瞬間保冷剤
- 最優先は計測と記録:体温・発症時刻・飲水量・尿回数・解熱剤の時間
- 補水:規定濃度で少量頻回、冷やしすぎない。吐後は10–20分休む
- 冷却:直接当てず短時間(不快軽減が目的)
- 受診判断:迷えば#7119(地域差あり)。赤信号は119
今日の5分の準備が、夜中の不安を減らします。
免責事項
本記事は医師の診断・指示に代わるものではありません。
一般的な情報提供を目的としています。
症状や既往歴、月齢・年齢によって対応は異なります。
製品は添付文書・用法用量を必ず確認し、迷ったら #7119 へ。
緊急性が高いと感じたら 119 を。

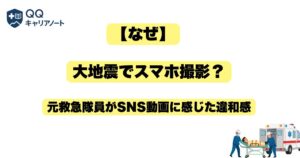
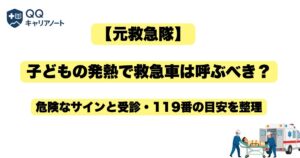
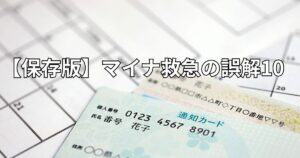
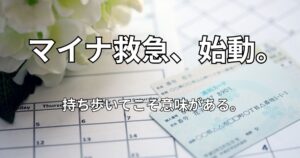
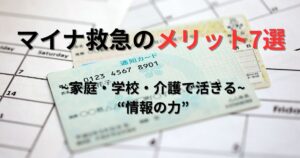
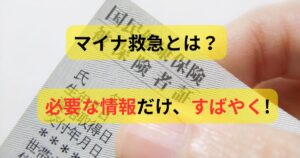
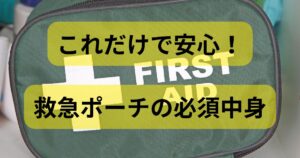
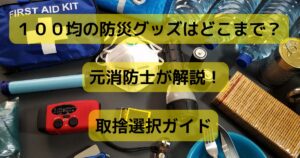
コメント