災害や大雪など、想定外の事態が起きたとき——
「♯7119にかけても全然つながらない」
「119番にかけたのに、いつまでも呼び出し音」
「救急車を呼んだけど、全然来ない…」
こうした声は、決して珍しくありません。
実際、私が救急隊員として勤務していた中でも、災害時や雪に不慣れな地域での大雪時には、119番も♯7119も非常につながりにくくなるという事態が何度もありました。
さらに、道路状況が悪化していれば、救急車はそもそも現場にたどり着けないということもあります。
なぜ119番がつながらない? 救急車が来ない?
- 通報が一気に集中し、回線がパンク
- 出場中の車両が多く、すぐに手配できない
- 道路の通行困難や渋滞で現場到着が大幅に遅延
- 病院側の受け入れも限界に達している
このような『非常時』には、いつものようにスムーズな対応ができなくなるのが現実です。
だからこそ必要な「判断力」と「知識」
こうした状況下で重要になるのが、
自分自身で医療機関を受診するかどうかの判断力
そして、そのための最低限の医療知識
何も専門家になる必要はありません。
ですが、 「この症状は自己受診でも大丈夫か」「これは救急を呼ぶべきか」 という目安を、ある程度理解しておくことは、非常時に大きな力になります。
自己受診を検討できるケース(あくまで一例)
- 軽い発熱や咳(顔色良好、食事・水分摂取が可能)
- 意識がしっかりしている打撲や捻挫(強い腫れや変形がない)
- 軽度の腹痛(会話が可能、冷汗や嘔吐を伴わない)
- 頭痛・めまい(持続せず、会話や歩行に問題がない)
逆に、以下のような場合はためらわず救急車を呼んでください。
- 意識がもうろうとしている/呼びかけに応じない
- 呼吸が苦しい、ゼーゼーしている
- 急な激しい胸の痛み
- 顔がゆがみ、ろれつが回らない(脳卒中疑い)
- 止まらない大量の出血
「受診ガイド」を活用しよう
実は、こうした『救急車を呼ぶべきか迷ったとき』に役立つ 全国版の救急受診ガイドや、各自治体が作成している受診目安のパンフレット・WEBサイトがあります。
例えば:
- 全国版救急受診ガイド「Q助」(総務省消防庁)
→ 症状を選択するだけで、緊急度を判定してくれるWEBツールです。
「いますぐ救急車」「早めに医療機関受診」などのアドバイスが表示されます。 - 都道府県・市町村ごとの受診ガイド
→ お住まいの地域で独自に作成されたガイドブックやフローチャートが配布されている場合があります。
→ 「〇〇市 救急 受診ガイド」などで検索してみてください。
▶︎ 事前に確認しておくのが“命綱”になるかもしれません
これらの情報を 平時のうちに確認しておくこと が、非常時の不安を減らし、的確な判断につながります。
知識が命を守る。準備が混乱を防ぐ。
「なんとなく不安だから救急車」ではなく、「これは自己受診でいいかも」「今は少し様子を見よう」と考えられるだけで、自分も、周りの人の命も守れる可能性が高まります。
また、普段から以下のような準備も効果的です。
- かかりつけの病院・近隣の救急対応病院をリストアップ
- 家族で「緊急時にどうするか」を話し合っておく
- 『お薬手帳』や持病・アレルギー情報の整理
- 全国版受診ガイドや地域のパンフレットを印刷して常備
最後に
119番は万能ではありません。
災害時や特殊な気象条件の中では、救急の機能も限界を迎えることがあります。
だからこそ、
「救急車が来なかったとき、自分はどうするか」
という“もう一つの選択肢”を持っておいてください。
元救急隊員として、現場のリアルを見てきた立場から、この“判断力”と“備え”の大切さを、どうしても伝えておきたいのです。
↓↓関連記事はこちら↓↓
救急隊がLINEで連絡してくることはあるのか?元救急隊員が語る“あり得ない理由”
【元救急隊員が伝える】救急車を呼ぶときに用意しておくと安心な持ち物リスト
救急車「呼ぶか迷ったら」どうする?つながらない#7119と備える知識
救急車が有料化される!?元救急隊員が語る背景とリアルな現場の声
交通事故に遭ったら救急車を呼ぶべき?元救急隊員が考える本当に必要な対応

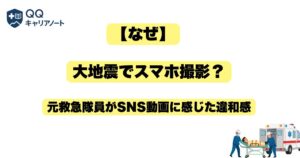
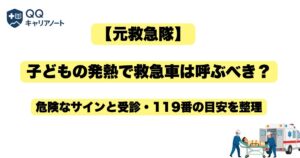
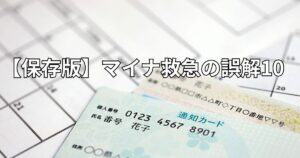
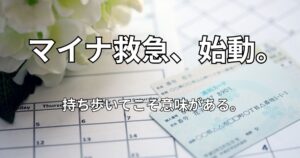
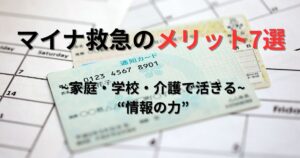
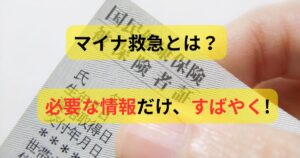
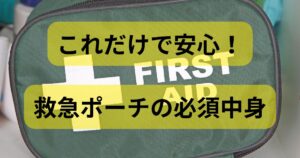
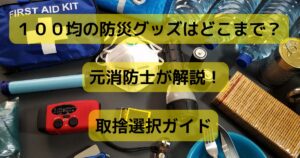
コメント