救急車といえば、サイレンを鳴らして現場に急行する姿を思い浮かべる方がほとんどでしょう。
しかし、実際には現場の状況によって、サイレンを鳴らさずにそのまま帰署することもあります。
元救急隊員として多くの現場を経験してきた私が、その理由と背景を具体的な実例とともに解説します。
基本はサイレンを鳴らして出場
救急車は、傷病者宅や事故現場に到着し、医療機関に搬送することを目的に運行します。
そのため、通常は必ずサイレンを鳴らして走行します。
これは緊急性の高い事案に迅速に対応するためのルールです。
また、救急車は法律上『緊急車両』として扱われます。
いわゆる緊急走行とは、サイレンを吹鳴し、赤色灯を点灯したうえで走行することを指します。
これらが揃って初めて、他の車両に道を譲ってもらえるなどの特例が認められるのです。
つまり、救急車は緊急車両である以上、サイレンを鳴らすことが必要不可欠であり、搬送に向かう際には必ず吹鳴して走行することになります。
サイレンを鳴らさずに帰るケース
しかし、すべての状況でサイレンを鳴らすわけではありません。
現場の状況によっては、静かに帰署することがあります。
以下のようなケースです。
1. 医療機関から引き上げるとき
当たり前ですが、傷病者を医療機関に搬送して引き上げる際にはサイレンは鳴らしません。
通常の車両と同じく、安全運転で消防署へ帰署します。
2. 社会死と判断された場合
隣人から「部屋の明かりが数日前から点いたまま」「最近異臭がする」「郵便受けに新聞がたまっている」といった通報が入ることがあります。
こうした場合は社会死(すでに亡くなって時間が経っている状態)であることも多く、警察から消防に通報が回るケースも少なくありません。
社会死と救急隊が判断した場合は、その場で警察官に引き継ぎ、搬送は行いません。
そのためサイレンを鳴らさずに静かに帰署します。
3. 傷病者や通報者が現場にいない場合
「路上で人が倒れている」との通報で出場することも多くあります。
ところが現場に到着すると人影はなく、通報者も立ち去っており、警察官と一緒に周囲を探しても見つからないことがあります。
こうした場合も、結果的にサイレンを鳴らさずに帰署することになります。
意外とあるケースです。
4. 傷病者が救急搬送を拒否した場合
「不安で救急車を呼んだが、隊員と話しているうちに楽になったので病院へは行かない」となる方も少なくありません。
実際、こうしたケースは想像以上に多いのです。
救急隊はその意思を尊重し、搬送を行わずに帰署します。
ただしその際には、「もしまた症状が悪化したらすぐに119へ」と必ず伝えてから撤収します。
まとめ
救急車は原則としてサイレンを鳴らして出場しますが、現場の状況によっては鳴らさずに帰るケースもあります。
これは決して「手抜き」ではなく、冷静な状況判断に基づいた対応です。
通報の内容だけでは現場の実態は分かりません。
ですから、サイレンを鳴らさず帰っていく救急車を見かけても、「何もしていない」とは思わないでください。
それには必ず理由があるのです。
↓↓関連記事はこちら↓↓
「救急車で運ばれた」――その表現、本当に正しいのでしょうか?
【なぜ?】救急車を呼んだのに消防車も来る理由とは|元救急隊員が解説
救急車が有料化される!?元救急隊員が語る背景とリアルな現場の声
「誰?」じゃなくて出てほしい!救急隊員からの電話には大切な理由がある
救急車が“遅い”のには理由がある!緊急走行の裏に隠された本当の事情
【必見】救急車で搬送された後の“帰り”はどうする?家族が知っておきたい準備と対策
救急隊は土足で室内に入るのか? 〜知られざる配慮とその理由〜

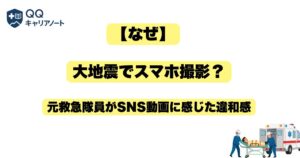
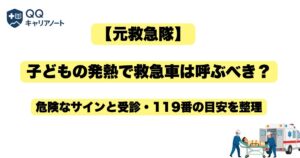
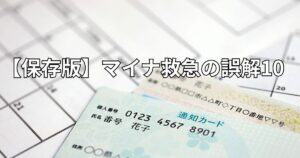
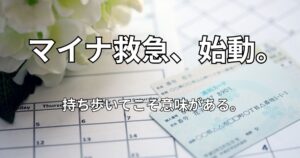
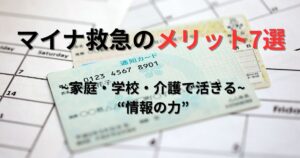
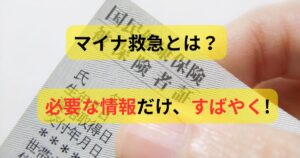
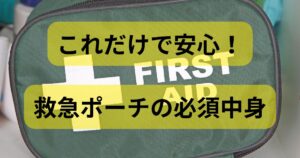
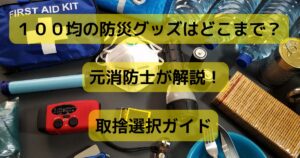
コメント