救急隊員としてのキャリアを通じて、私が何度も感じたのは『接遇の重要性』です。
救急隊員と聞くと、まず真っ先に思い浮かぶのは、急患への素早い対応や、適切な処置、専門知識を活かした救命活動だと思います。
もちろん、これらは救急業務において欠かせないものです。
しかし、実務の中で最も重要だと感じたのは、実は「接遇」でした。
接遇とは?

接遇とは、簡単に言えば「おもてなしの心」です。
救急車が駆けつける現場では、患者やその家族は、誰しもが不安や恐怖に包まれています。
そんな中で、私たちが患者やその周りの方々にどのように接するかが、彼らの心理的な安心感を大きく左右します。
また、救急車を呼んだ際に「軽症かもしれない」「こんなことで呼んでしまって申し訳ない」と恐縮している人に対しても、接遇は欠かせません。
こうした患者や家族は、自己判断で救急を呼んだことに負い目を感じることが多く、こちらの接遇が適切でないと、不必要なトラブルや誤解を生む可能性があります。
💡 関連記事:態度の誤解が生まれる理由もあわせて読むと理解が深まります

接遇がトラブルを避ける鍵に

救急隊員として、軽症だと思われる患者に対しても、常に丁寧な対応を心掛けることが大切です。
患者が「呼んでしまって申し訳ない」と思っているとき、私たちが不親切な態度をとれば、彼らはさらに申し訳なさを感じ、時には不満や怒りを抱くことすらあります。
しかし、ここで温かく寄り添い励ましの言葉や安心感を与えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、
「大事に至らなくて本当に良かったです。救急車を呼んでいただいて正解でしたよ」
といった一言が、相手の不安を和らげ信頼関係を築く手助けになります。
結果として、職務も円滑に進み、救急現場全体がスムーズに機能するのです。
接遇の重要性とその実践

私は元救急隊員として、隊長、隊員、機関員のすべての役割をこなしてきましたが、どの役割でも接遇は非常に重要でした。
患者やその家族、救急車を要請した人に対してだけでなく、搬送先の医療機関に連絡する際や申し送り時に対する医師や看護師に対しても、接遇の重要性を認識しました。
救急活動時には欠かすことのできないスキルと言っても過言ではありません。
例えば、私は機関員として活動していた際、店の前に救急車を止めることもありました。
その時には必ず店の方に一言声をかけることを心掛けていました。

小さな配慮ですが、こうした行動が現場のスムーズな進行を助け地域との信頼関係を築くきっかけにもなりました。
また、現場で手伝ってくれた人や通報者には必ずお礼を言うことを忘れないようにしていました。
感謝の言葉一つで支援者との関係が良くなり、次回も協力してもらいやすくなるのです。
隊長を務めていた時には、患者さんに対してまず自分の名前を名乗って接することを徹底していました。
初対面での緊張感を和らげるとともに、自分がどのような立場でここにいるのかを明確にすることで、患者さんの不安を少しでも軽減することができました。
このような小さな接遇の積み重ねが、現場での信頼感を高め患者やその家族の安心感に繋がります。
さらに、家族への配慮も忘れずに行いました。
家族は冷静ではないことがほとんどのため、持ち物の確認や家族からの情報を得る際には、患者から少し離れて話を聞くことを意識していました。
家族の不安を軽減しつつ、適切な情報を得ることで患者のケアに役立てることができました。
このような接遇の工夫が、現場での信頼関係を築く要因となります。

相手の立場に立った考えができるかどうかが鍵です。
疲労が増し、イライラする気持ちが募ったとしても接遇をないがしろにしてはいけません。
むしろ、そういったときこそ接遇を重視しなければならないのです。
得てして、そういう場面で接遇を無視したときに限って、トラブルを招く恐れがあります。
すべての人に対して同じように接することが重要ですが、極端にへりくだる必要はありません。
具体的な接遇のポイント
接遇には重要な3つのポイントがあります。
これらをしっかりと押さえることで、現場での対応が格段に良くなります。
- 相手の立場に立った行動
- 落ち着いた声掛けと表情
- 状況説明の明確さ
🗣 現場でそのまま使える一言テンプレ
- 到着直後:「救急隊です。◯◯と申します。今からお体の状態を確認しますね」
- 処置中:「いま酸素を付けます。苦しくなったらすぐ教えてください」
- 家族へ:「大事に至らなくて本当に良かったです。救急車を呼んで正解でしたよ」
- 協力依頼:「安全のためここだけスペースをください。ありがとうございます」
- 終了時:「ご協力ありがとうございました。心配なときは#7119へご相談ください」
🧩 NG→OK 言い換え表
| シーン | NG | OK |
|---|---|---|
| 退避依頼 | どいてください! | 安全のためこちら側にお願いします |
| 否定 | それは違います | 念のため病院で確認しましょう |
| 搬送判断 | 行きます | 念のため病院で診てもらいましょう |
| 待機 | ちょっと待って | 今から血圧を測ります。30秒だけこの姿勢でお願いします |
救急隊の申し送り(実際の現場の流れ)
私が現役時代に行っていた申し送りは、とてもシンプルで実践的なものでした。
- 病院への受け入れ要請(電話口)
- 傷病者の年齢・性別
- 主訴(例:胸痛、呼吸困難など)
- 発症状況・経過の概要
- バイタルサイン
- 受け入れ確認
- 医師・看護師への引き継ぎ(現場到着時)
- 傷病者の概要(年齢・性別)
- 発症状況(いつから、どうなったか)
- 既往歴(持病や服薬など)
- バイタルサイン(意識、呼吸、脈拍、血圧、SpO₂など)
これは海外の『SBAR』のような形式的なフレームワークではありませんが、限られた時間で必要な情報を簡潔に伝えるという点では共通しています。
現場で培われたシンプルな手順だからこそ、混乱せず正確に引き継げるのです。
接遇が生む信頼
救急現場は、時間との闘いであると同時に、信頼関係を築く場でもあります。
傷病者が安心し、救急隊員に身を任せられるかどうかは、その瞬間の接遇にかかっています。
接遇がしっかりしていると処置への協力もスムーズになり、結果的に救命率を高めることにも繋がるのです。
救急車の適正利用と相談窓口
ただし、どんな場面でも救急車を呼ぶことが適切かというと、それは必ずしも正解ではありません。
軽度の症状で救急車を利用することが増えたことで、本当に緊急を要する患者に対応するリソースが不足してしまうケースも少なくありません。
そのため、救急車の適正利用を意識し、どのタイミングで呼ぶべきかを判断することが大切です。
現在では、多くの自治体が「#7119」などの救急相談センターを設けており、緊急性があるかどうかを判断できない場合には、こうした窓口を活用することが推奨されています。
救急車が必要かどうか迷った場合は、まず相談センターに連絡することで、適切なアドバイスを受けることができ、結果的に救急車の適正利用にも繋がります。
👉 救急車を呼ぶべきか迷ったときの相談窓口について詳しくはこちら

🧰 もしもの備えにおすすめ(商品紹介)
救急現場の不安を減らす日常の備えは小物からでOKです。
最後に
救急車を呼ぶような緊急時には、誰もがパニック状態に陥りがちです。
そんな中で、いかに患者やその周囲の人々に寄り添い、安心を与えることができるか。
それこそが、救急隊員としての最大の使命であり、接遇が最も重要なスキルだと確信しています。
命を救うために必要な技術や知識はもちろん重要ですが、それを最大限に活かすためには人としての温かさが欠かせないのです。
そして、救急車の適正利用に対する理解を広めることも、私たちの役割の一つだと感じています。
救急車を必要とする場面での迅速な対応と、必要なリソースを確保するために救急相談窓口の利用を推奨することも大切です。
🔒 家計の不安も小さく
PR 広告・プロモーションを含みます
救急車は無料でも、医療費はゼロじゃない
突然の搬送で発生する入院・通院・差額ベッド代…。
無料の保険見直しで、今の備えで足りるか一度チェックしてみませんか?
↓↓関連記事はこちら↓↓
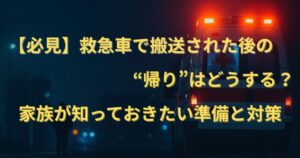










コメント