突然、家族や身近な人が倒れて119番通報をしたとき、
「救急車が来るまで何をすればいいの?」
と不安になる方は多いのではないでしょうか。
実はこの“数分間”に行う準備や対応で、その後の救命や搬送のスムーズさが大きく変わります。
この記事では、救急現場で長年活動した経験から、誰でもできる「救急車が来る前にやってほしいこと7選」を、わかりやすくまとめました。

1. 場所を正確に伝える
- 住所だけでなく、近くの目印になる建物や交差点名を伝えると、救急車が迷わず到着します。
- もし可能なら、案内に出られる人が外で待って救急隊を誘導していただけると助かります。
- 通報者は電話を切らず、いつでも出られる状態にしておきましょう。
2. 搬送ルートを確保する
- 搬送に使うのは、玄関などの進入口から傷病者のいる場所までのルートです。
- このルートにある靴・荷物・マット・段ボール・ベビーカーなどを整理して、通れるようにしておくと搬送がスムーズになります。
- 夜間は照明を点けて明るくしておくことも大切です。
3. 情報を整理して準備する
救急隊が最初に必要とするのは、傷病者に関する情報です。
あらかじめ準備しておくと処置や搬送がスムーズになります。
- 名前・年齢・生年月日・住所
- 発症した時間や状況(例:食事中に突然倒れた)
- 持病やかかりつけ病院
- 服用している薬(お薬手帳や薬の現物)
- 健康保険証、診察券

4. 状態の変化を伝える
救急車を呼んだあとも、傷病者の状態を観察することが大切です。
- 呼びかけに反応するか
- 呼吸はあるか
- 顔色はどうか(青白い・赤い・紫色っぽい)
- けいれんが起きていないか
変化があれば、再度119番に通報して「〇分にこう変わった」と伝えてください。

5. 心肺停止が疑われる場合は心臓マッサージを
- 反応がなく、普段どおりの呼吸がなければ、胸の真ん中を強く・速く・絶え間なく押す(1分間に100〜120回)。
- 近くに協力者がいれば協力し合い救急隊が到着するまで継続してください。
- わからない場合は、119の指令員が電話でやり方を教えてくれます。その指示に従ってください。
- 近くにAEDがあれば使用し、音声の指示に従えば大丈夫です。
6. 傷病者が楽な体勢にする
一番大切なのは、傷病者本人が一番楽だと感じる体勢を取ってあげることです。
- 呼吸が苦しそうなら少し上半身を起こす。
- 嘔吐や意識がぼんやりしている場合は横向き(回復体位)にして窒息を防ぐ。
- 出血していれば清潔なタオルで直接押さえる。
- 毛布やタオルで体を温め、冷えを防ぎましょう。
※意識がはっきりしない傷病者に水や食べ物を与えるのは危険なので避けてください。
清潔なガーゼや手袋、人工呼吸用の簡易マスクがあるだけでも“いざという時”の安心感が違います。
最低限の応急用品を1セット、家に置いておきましょう。
▼ 応急処置に役立つ常備品
※ 人工呼吸は状況により不要/不適切な場合があります。胸骨圧迫(強く・速く・絶え間なく)が最優先です。迷ったら119の指令員の口頭指示に従ってください。
7. ペットや同居家族の対応をしておく
- ペットは大切な家族です。ですが、ペット自身も「家族を守ろう」として、救急隊員に噛みついてしまう可能性があります。
- もし救急隊員が噛まれてしまうと、救急活動は一時中断し、別の隊が必要になることも。その間に傷病者への対応が遅れてしまいます。
👉 そのため、ペットは必ずゲージに入れるか、別の部屋に移動させてください。 - 小さな子どもがいる家庭では必要に応じて、救急隊が病院に「一緒に連れて行けるか」を確認することもあります。しかし、介護中の高齢者がいるご家庭など、緊急時にどうするかを事前に決めておくと安心です。


救急車を呼ぶ場面は突然やってきます。ふだんの備えがあるだけで、当日の不安はぐっと減らせます。
▼ 普段からの備え(ヘルスケア)
※ パルスオキシメーターは国内の医療機器認証が明記された正規品を推奨します。測定結果は目安であり、症状が強い場合は数値にかかわらず119番通報や受診を検討してください。
まとめ
救急車を呼んでから到着するまでの数分間に、できることはたくさんあります。
- 場所を正確に伝える
- 搬送ルートを確保する
- 必要な情報や持ち物を準備する
- 状態の変化を観察して伝える
- 必要があれば心肺蘇生やAEDを使う
- 傷病者が楽に呼吸できる体勢にする
- ペットや同居家族への対応をしておく
どれも難しいことではなく、少しの準備で救命や搬送がぐっとスムーズになる行動です。
無理のない範囲で構いません。
落ち着いて、できることから取り組んでみてください。
不安なときに役立つ関連記事も置いておきます。状況に合わせて読んでみてください。


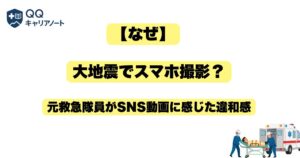
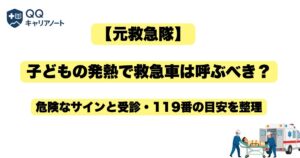
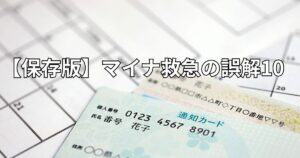
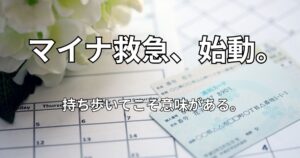
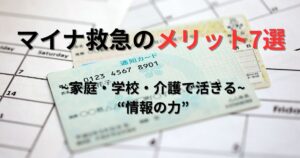
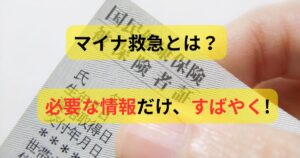
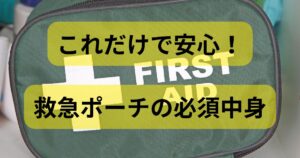
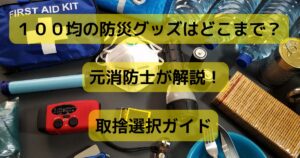
コメント