救急隊の対応について、「態度が悪い」「冷たい」「偉そう」と感じたことがある人もいるかもしれません。
特に、緊急の場面では、救急隊員の言動が素っ気なく感じられることがあります。
しかし、彼らの本心はどうなのでしょうか?
私は元救急隊員として、数え切れないほどの現場を経験してきました。
その中で、救急隊の態度に誤解が生じる瞬間を何度も目の当たりにしました。
今回は、なぜそう感じるのか、そして救急隊員が現場で何を考えているのかを本音で語りたいと思います。
💡 先に「接遇=信頼づくり」の基本を押さえると、この先がスッと入ります

救急隊の態度が悪いと感じる瞬間
救急隊の対応が冷たく感じられる場面はいくつかあります。
例えば、傷病者や家族への説明が短く、事務的に聞こえることがあるかもしれません。
これは、救急隊が患者の状態を素早く把握し、適切な処置を行うために、どうしても無駄な時間を省こうとするからです。
また、指示が強めの口調になってしまうこともあります。
特に、心肺停止や意識障害などの緊急性が高い場面では、迅速な対応が求められます。
そのため、家族や周囲の人に対して「どいてください!」「これを押さえて!」と強い口調になることがありますが、決して威圧的になろうとしているわけではありません。
さらに、会話が少なく無愛想に感じることもあります。
これは、隊員が処置に集中しているからこそ起こることであり、決して患者を軽視しているわけではありません。
例えば、救急車内では血圧測定や点滴、心電図の確認など、やるべきことが多く、話す余裕がないこともあります。
なぜ救急隊の態度はそう見えてしまうのか?
このような態度が生まれる背景には、時間との戦いがあることを理解していただきたいです。
救急現場では、一秒でも早く病院に搬送することが患者の命を救うことにつながります。
そのため、どうしても会話の優先度が低くなり、説明不足になってしまうことがあります。
また、救急隊員自身も精神的・肉体的にギリギリの状態で活動していることも理由の一つです。
長時間の勤務や、連続する出動によって疲労がたまり、時には余裕のない対応になってしまうこともあります。
👉 制度・社会的背景も知っておくと誤解が減ります(読みやすい解説)


🧰 もしもの時の“備え”は小物から
救急隊が心掛けるべきこと
とはいえ、救急隊員側も誤解を防ぐために努力するべき点は多くあります。
まずは患者や家族に対して名乗ること、目を見て話すことが重要です。
これだけで、相手に与える印象は大きく変わります。
また、可能な限り短くても丁寧な説明を心掛けることも大切です。
「今、傷病者の状態を確認しています」「すぐに病院へ向かいます」など、一言添えるだけで安心感を与えられます。
さらに、隊員同士のやりとりにも配慮が必要です。
救急隊員同士の会話が専門用語ばかりだと、家族は何をしているのか分からず、不安を感じることがあります。
そのため、できるだけ分かりやすい言葉を使うことも、態度の誤解を防ぐ一つの方法です。
そして、最も大切なことは、何件目の出場であっても、同じように真摯に患者に向き合うことです。
先輩や上司からよく言われた言葉があります。
「どんなに疲れていても、最初の出場のように対応する」
「今日10件目の出場であっても、救急車を呼んだ人にとっては、本当に困って呼んだ1件なのだ」と言われました。
救急隊員にとっては何度目の出場でも、通報者にとっては一生に一度の経験です。
その1回の対応が冷たかったり、ぶっきらぼうだったりした場合、相手はどんな気持ちになるでしょうか?
そのため、「1回1回の対応を大切にする」という心構えを常に持っていることが、救急隊員として最も大切だと教えられました。
👉 接遇を「現場でどう実践するか」をさらに詳しく

PR 広告・プロモーションを含みます
救急車は無料でも、医療費はゼロじゃない
突然の搬送は誰にでも起こり得ます。入院・通院・差額ベッド代…。 無料の保険見直しで、今の備えで足りるか一度チェックしてみませんか?
※制度・金額は地域や条件で異なります。リンクはアフィリエイト広告を含みます。
まとめ:救急隊の態度は本当に悪いのか?
救急隊の対応が「冷たい」「態度が悪い」と感じることがあるかもしれません。
しかし、その背景には、迅速な対応を求められる過酷な現場の現実があります。
決して威圧的になりたくて言っているわけではなく、傷病者を最優先に考えて、時間を無駄にしないようにしている結果、そう見えてしまうことがあるのです。
とはいえどんなに過酷な状況でも、救急車を呼んだ人にとってはその1回の経験が非常に重要であることを忘れてはいけません。
どんなに疲れていても、「1回1回の対応を大切にする」という気持ちを持ち続けることが、救急隊員としての基本です。
もし過去に救急隊の態度が悪いと感じたことがあれば、その背景にある事情にも少しだけ思いを馳せていただけたらと思います。
そして、現役の救急隊員の皆さんには、「何件目の出場でも、1件1件を大切に」という言葉を心に刻んでほしいと願っています。
↓↓関連記事はこちら↓↓

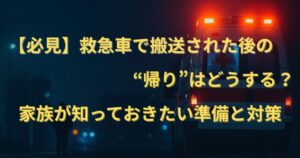










コメント